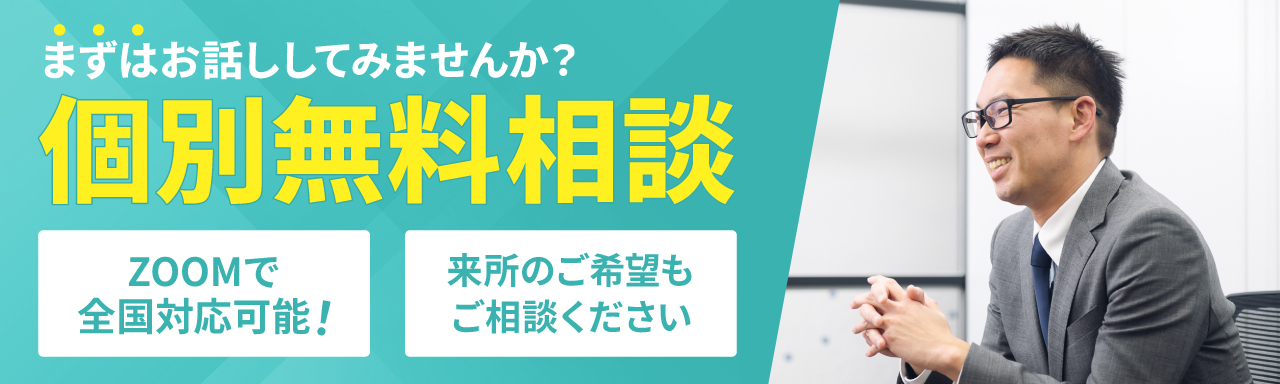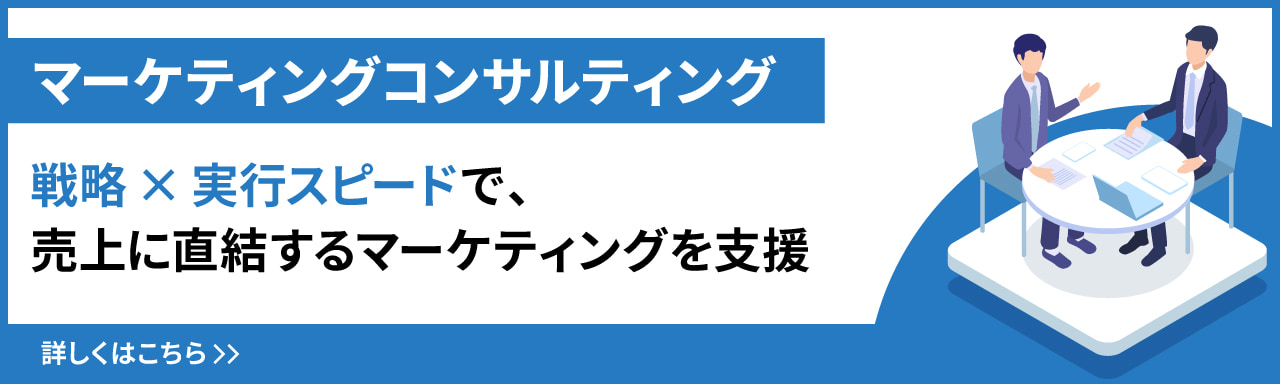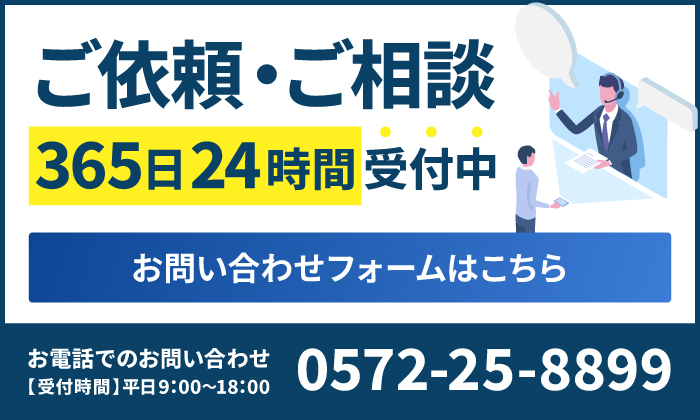コラム
不確実な時代を勝ち抜く!マーケティングに効く『エフェクチュエーション』とは?

マーケティングに関わる方なら、「緻密な戦略を立てたのに、結果が出ない」「トレンドの移り変わりが早すぎて、追いかけきれない」など、こうした戸惑いを一度は経験されたことがあるのではないでしょうか。
近年、変化のスピードが加速し、計画や予測に基づく従来型のマーケティングアプローチだけでは対応しきれない場面が増えています。
そんな中で注目されているのが、「エフェクチュエーション(Effectuation)」という新しい考え方です。もともとは起業家の思考モデルとして紹介されましたが、今やマーケティング領域でも大きなヒントを与えてくれる考え方として注目されています。
この記事では、エフェクチュエーションの基本的な考え方から、なぜ今必要とされているのかについて、分かりやすく解説します。
エフェクチュエーションとは

エフェクチュエーションとは、「今あるものを起点に、できることから始め、未来を形作っていく」考え方です。
これは、「市場を予測し、ゴールを決め、それに必要な資源を集めて動く」といった、従来のコーゼーション(Causation)とは対照的です。
2つの考え方を簡単にまとめると下記の通りです。
- コーゼーション:ゴールから逆算して進める
- エフェクチュエーション:手元の資源から始めて、進みながらゴールをつくる
料理で例えるなら、レシピを決めて材料を買いに行くのがコーゼーション、冷蔵庫の中身から何が作れるかを考えるのがエフェクチュエーションです。
マーケティングにおいても、このような「あるものでできることから始める柔軟なアプローチ」が、今後ますます重要になります。
エフェクチュエーション3つの資源
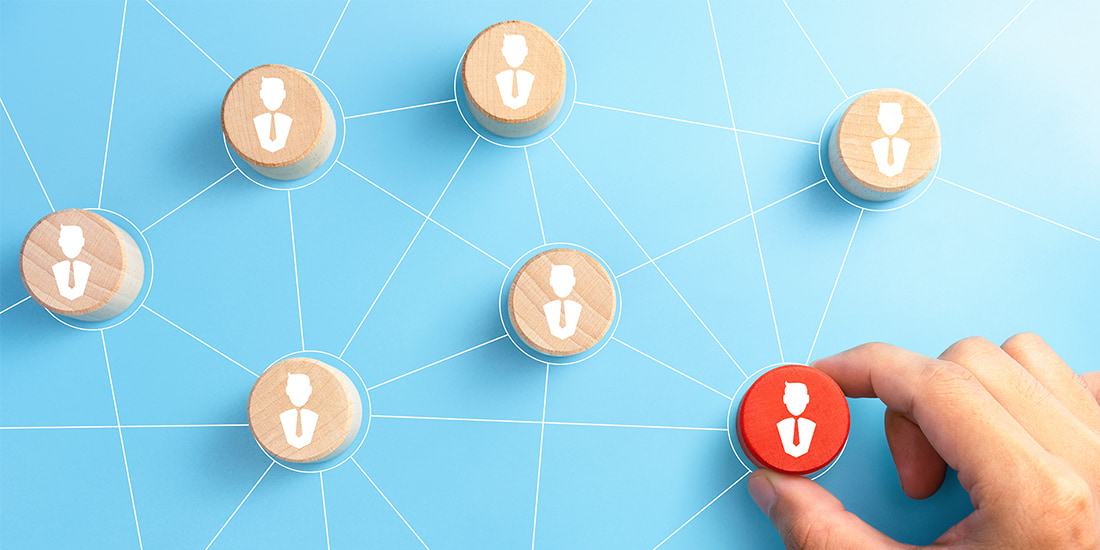
エフェクチュエーションの考え方では、最初に「自分たちがすでに持っているもの=手持ちの資源」から始めることが基本とされています。これらの資源は、将来のゴールに向かって進む足がかりであり、材料でもあります。
その資源は大きく3つに分類されます。
1. 自分が誰か (Who I am)
「自分が誰か」は、自分自身が持つ価値観や信念、個性といったアイデンティティに関わる要素です。
- 何を大切にしているのか
- どんな思いを持ってこのビジネスをしているのか
- 自社のカルチャーや歴史はどんなものか
この自分たちらしさは、マーケティングにおいてはブランドの核になります。
「なぜこの商品を届けたいのか」「誰にどんな価値を届けたいのか」といった想いが起点になることで、施策の方向性や言葉のトーンが自然に定まってきます。
2. 自分が知っていること (What I know)
「自分が知っていること」は、これまでに培ってきた知識・経験・専門性のことを指します。
- 業界知識、技術的スキル、顧客理解
- 競合との違いに気づける視点
- 社内で蓄積されたナレッジやノウハウ
マーケティングでは、「顧客が本当に困っていることを知っている」ことが大きな強みになります。データやツールだけでなく、現場で得た「肌感覚」のような知識も、施策の引き出しとして活かせる大切な資源です。
3. 自分が誰を知っているか (Whom I know)
「自分が誰を知っているか」は、人とのつながりです。社内外を問わず、協力してくれる仲間や関係性も大きな資源とされています。
- 顧客やパートナーとの信頼関係
- 社内の他部署とのつながり
- SNSのフォロワー、コミュニティ、過去のクライアント
特に現代のマーケティングでは、「誰とつながっているか」が情報の広がり方や施策の反響に直結します。最初から大きなリーチを狙うのではなく、「今つながっている人との対話の中から、次の一手が生まれる」それがエフェクチュエーション的なアプローチです。
エフェクチュエーションの5つの原則

エフェクチュエーションは、ただ「3つの資源」を持っているだけではなく、その資源をどのように使うかが大切です。そのために提唱されているのが、「5つの原則」です。これらは、未来が不確実な中でどう行動し、判断すればよいかを教えてくれる指針です。
1. 手中の鳥の原則 (Bird-in-Hand Principle)
「未来に何をしたいか」ではなく、「今、手元に何があるか」からスタートしましょう、という考え方です。
マーケティングでは理想の顧客像や目標売上を追いかける前に、まずは「今持っている商品」「既存顧客の声」「チームの強み」など、目の前にある資源を活かすことから始めるのが効果的です。これにより、無理のないスタートが切れ、早く動き出せるメリットがあります。
2. 許容可能な損失の原則 (Affordable Loss Principle)
未来の大きな成功や利益を期待するのではなく、「損失として許容できる範囲」を明確にして判断することを意味します。
マーケティング施策においては、最初から大きな投資をするのではなく、リスクを抑えた小さな実験から始めることがポイントです。
こうすることで、万が一失敗してもダメージは最小限に抑えられ、次の施策に素早く活かせます。
3. クレイジーキルトの原則 (Crazy Quilt Principle)
「ひとりで全てをやろうとせず、協力できる仲間を増やしていく」ことが重要だという考えです。
マーケティングでは、社内の他部署や顧客、外部のパートナー、さらにはファンやコミュニティとも積極的に関係を築きましょう。
一緒に価値をつくり上げていくことで、より豊かなアイデアや新しい可能性が生まれます。
4. レモネードの原則 (Lemonade Principle)
「予期せぬ出来事やトラブルも、ポジティブに捉えて活かそう」というマインドセットです。
マーケティングの世界では、思った通りに反応が得られないこともよくあります。
そんなときこそ、「想定外の反応から新たな学びを得るチャンス」と考え、柔軟に施策を調整していく姿勢が大切です。
5. パイロット・イン・ザ・プレーンの原則 (Pilot-in-the-Plane Principle)
「未来は他人に決められるものではなく、自分たちの行動で創り出すもの」という考えです。
マーケティングでは、市場のトレンドや競合動向に振り回されるのではなく、自社の強みや顧客との関係性をもとに「自分たちの未来をデザインする」という積極的な姿勢が求められます。
なぜ今エフェクチュエーションが必要なのか?

現代のマーケティングは、変化のスピードが速く、不確実性が高まっています。こうした環境では、従来のように「長期的に計画を立てて、決まった道筋を忠実に進む」だけでは、柔軟に対応しきれません。
そこで求められるのが、エフェクチュエーションの考え方です。
小さな実験を繰り返し、顧客やパートナーとの対話を通じて価値を共に創り出していく姿勢は、変化の激しいマーケティング現場に非常にマッチしています。
つまり、エフェクチュエーションは「不確実な時代を乗り切るための羅針盤」として、今こそ取り入れるべき思考法なのです。これにより、リスクを抑えながらも素早く動き、想定外のチャンスを逃さずに、より確実に成果を積み上げていけるようになります。
まとめ

エフェクチュエーションは、「正しく計画する」ことよりも、「柔軟に進みながら学びを得る」ことに重きを置きます。
「今あるものから、できることを、まず一歩」この視点を取り入れることで、見えてくる景色はきっと変わっていくでしょう。
もし、エフェクチュエーションの考え方を具体的なマーケティング施策にどう活かせばよいか迷われているなら、ぜひSMCマーケティングにご相談ください。
皆さまが抱えている課題やお悩みを、私たちと一緒に解決していきましょう!
貴社の強みを活かしたマーケティング戦略を一緒に考え、SMCマーケティングが伴走します。